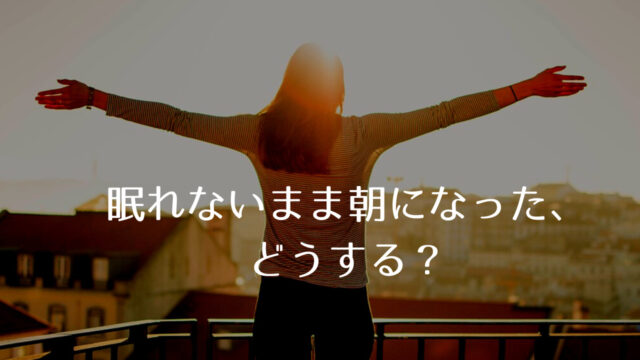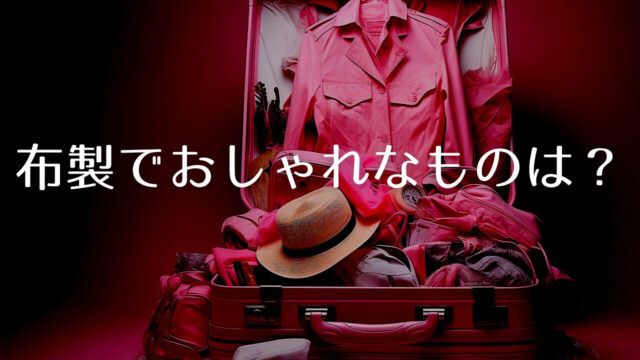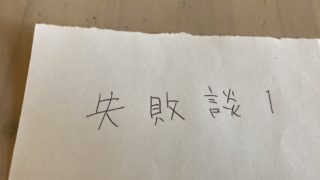退職が決まって、退職届を書こうとしたときに、
?!
何に書けばいい?
↓
検索
という行動になるようです。
それはそうですよね^^;
なかなか提出しないものですから。
履歴書は履歴書の用紙があってそこに書けば良いのですが、退職するときには決まった用紙ってあるのでしょうか?
今回はそんな退職届の用紙と封筒について調べてみました。
など、そんな疑問を解決していきましょう。



目次
退職届の用紙は100均で買える?

退職届の用紙ってどんなものを使ったらよいのでしょうか?
一番のおすすめは白紙の便箋です
罫線の入った紙、または真っ白なコピー用紙も良いですね。
100均でも買えるものがありますよ。
100均で買える退職届の用紙

100均ショップに行って退職届の用紙を買おうと思ったら、文具コーナーに行きますよね。
そこで探してみましょう。
- 白い便箋
- 罫線の入った便箋
- コピー用紙
というものが退職届を書くときに使えます。
便箋に罫線(けいせん:行の線)あり?なし?

でもその便箋の中にも、
- 罫線が入っているもの
- 入っていない白紙のもの
があります。
どちらが良いのでしょうか?
罫線がないと、縦書きに書いたときになんだか曲がってしまったり、全体が斜めになってしまったりと文字をそろえるのも難しいのは正直なところですよね。
なので、
罫線が入ったものを選ぶほうが無難です
また便箋を選ぶ場合には、カラフルなものやイラストなどが入っているものはNGです。
シンプルなものを選んでくださいね。
また、
手書きではなく、パソコンで作成する場合には罫線のないものを選びましょう。
サイズはA4?B5?

白紙のコピー用紙を選ぶなら、サイズはどのサイズが良いのでしょうか?
A4?B5?
パソコンで作る場合にはA4用紙を使うことがほとんどですが、B5でも作れないことはありませんよね。印刷するときにサイズを注意すれば問題ありません。
退職届は基本的にはどちらでもかまわないというのが一般的ですが、どちらか迷ったときには、
B5を選ぶのが無難です
退職届は書いたらそのまま提出するのではなく、封筒に入れて出しますよね。
封筒に3つ折りや4つ折りで入れることを考えると、B5のほうが入れやすいという理由もあります。
退職届を入れる封筒のサイズは?入れ方は?

退職届を書く用紙を選んで、退職届を書きます。
その後、そのまま提出するわけではありません。
用紙は3つ折りや4つ折りにして封筒に入れて提出するのがビジネスマナーですね
その封筒について、見ていきましょう。
どんな封筒を選ぶ?

まず、退職届を入れる封筒は、
- 白色
- 二重
- 郵便番号の記載欄がない
という条件を満たした封筒を選びましょう。
ビジネスの場面で使われる封筒は白か茶色が多いのですが、退職届を入れるのは「白」が良いのです。
茶色の封筒は、「領収書など事務処理のために」使われることがほとんどです
また、
「二重の封筒」を選ぶのは、
透けて中身が見えないようにするためです
「郵便番号の枠」がついているものも、退職届には不向きな封筒です。
真っ白の柄の入っていない長封筒を選ぶようにしましょう。
退職届を入れる封筒のサイズは?

100均ショップや文房具店などで見かける封筒にはサイズが書いてあるのをご存じですか?
「長形3号」「長形4号」
といった風に書いてあるのがそれです。
どのサイズを選んだらよいかというのは、退職届を書く用紙によって違ってきます。
用紙がA4サイズなら
封筒は「長形3号」というサイズを選びます
そうすると3つ折りや4つ折りにして入れるときにピッタリサイズなのです。
長4の封筒よりも大きいので持ち運びには少し不便さがあるかもしれませんが、退職届をパソコンで作って出す場合には、ちょうどよい大きさなのでこちらを選びましょう。
また、
B5のサイズの用紙なら
封筒は「長形4号」というサイズを選びます
用紙を3つ折りにして入れるとピッタリです。
このサイズの用紙と封筒を使うと、まず、コンパクトです。
ジャケットの内ポケットにも入れられて、スマートに退職届を出すにも便利かと思います。
封筒の書き方

白い封筒に何も書かずに提出するのは、これもNGです。
書き方は、
- 封筒の表に「退職届」と大きめの字で封筒の中央部分に書きます。
- 裏には、自分の所属部署とフルネームを左下に書きます。
「退職届」や「自分の名前」などは「縦書き」にします。
書くときには黒のボールペン、または万年筆で書くようにします
筆ペンやサインペンなどを使う人もいますが、文字が目立ちすぎるのであまりおすすめできません。
文字の大きさも目立ちすぎるような大きさは避けましょう。
用紙を封筒に入れる方法

退職届を書いた用紙を封筒に入れるときには、用紙を3つ折りするのが一般的です。
三つ折りにするときには、次の順序で折ってみましょう。
- 用紙の下3分の1を折ります
このときに、書面が内側になるようにおります。 - 用紙の上3分の1を覆いかぶせるように折ります
- 折った用紙を左回り90度回転させ、裏向きに準備した封筒にそのまま入れます
このようにすると、用紙の右上の角の裏と封筒裏の右上が重なるようになります。
ここがポイントです。
折るときには定規を使うとまっすぐにきれいな折り目をつけることができます。
角はきっちり合わせるようにしましょう。
また、入れるときにしわしわにならないよう、丁寧に取り扱うということも必要ですね。
提出するまで時間があるというときにも、ずっと内ポケットに入れておくよりも、降り曲がらないようなところに保管しておくという工夫も必要です。
これらの理由は、
こうした一つ一つが誠意として見られるからです
しわしわになった退職届を受け取る側はどう思うでしょうか?
受け取る人の立場に立って考えてみるのも良いですね。
封筒の封はする?しない?

封筒に入れたら、封をするかどうかで迷う人も少なくありません。
これは、
どちらでも良い
というのが一般的な答えです。
また封はしないという意見も多いです。
ただし、のり付きの封筒の場合、つまりシールになっているものですね。
こうした場合は封をして、封の上から「〆」と書いておきます。
封をしない場合でも上のフラップ部分は折り曲げておきます。
退職届を郵送で出すときには封筒はどうする?

退職届を「郵送で送る」ということもあり得ます。
それは、
「病気でどうしても会社に行けない」
「精神的に行けない」
「もう行きたくない」
例えばこんな状況ですよね。
この場合、
「退職代行を使う」という方法もあるので、(前書きでも少し触れましたが)それは最後の項で紹介したいと思います。
では、退職届を郵送で送る時には封筒はどうしたらよいのでしょうか?
退職届の用紙を「退職届」と書いた封筒に入れる。
これは変わりません。
しかし、このままではさすがに送れませんよね^^;
なので、
封筒に入った退職届を、さらに大きい封筒に入れて郵送する
ということになるわけです。
退職届の封筒が長形4号である場合は、長形3号の封筒にすっぽり入りますから、その封筒に入れるとよいでしょう。
一方、退職届の封筒が長形3号の場合は、それよりも大きい封筒、定形外の角5号という封筒が適当です。
郵送用の封筒は郵便番号の枠が付いていても良いですし、茶色の封筒でも大丈夫です。
郵送で退職届を送るときのマナー

郵送で退職届を出すときにもマナーを守って送るとその人の誠意を見せることができます。
どんな点に注意したらよいでしょうか?
宛名の書き方
表面に宛名を書きます。
宛名は、
- 会社名
- 部署名
- 上司の名前
以上ををはっきりと書いておきます。
この時の宛名は誰にするのか?この点は、事前に会社側へ確認しておく必要があります。
基本的には、
- 直属の上司
- 人事課
でしょう。
また、
宛名の左下には「親展」と赤字で書きます。
これは、
宛名本人以外は開けないでください
という意味を持っている言葉です。
宛名本人が開けるようになっているものなので、他の人が開けて誤解を招くことのないように、また退職届がきちんと処理されるためにも「親展」と必ず書いておきましょう。
そして封筒の裏面にの左下に、自分の住所と名前を書きます。
封をして、上から「〆」も書いておきましょう。
添え状をつける
郵送で退職届を入れた封筒だけを送ったら、受け取った側はどう思うでしょうか?
やはり、一言挨拶が欲しいですよね。
それがないとなんだか寂しい思いにもなりますし、社会的には常識がない人と思われても仕方がありません。
簡単でも良いので、添え状をつけて送るようにしましょう。
添え状は退職届の封筒の上において、郵送用の封筒に入れます
例えばこのような感じです。
【添え状の例文】
株式会社〇〇 ○○部 ○○課 上司の名前 様
拝啓 貴社ますますご清栄のことと存じ、お慶び申し上げます。
このたび一身上の都合により退職させていただくことになりました。
突然な退職により多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
同封のとおり、退職届を提出させていただきますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。
長い間(短い間ではございましたが)大変お世話になりました。末筆ながら、貴社のご健勝をお祈り申しあげます。
敬具
○○部○○課 自分の名前
参考にしてください。
郵送は郵便局で
切手を自分で貼って出してしまうのも良いのですが、
もし料金不足なんていうことがあると、会社側に迷惑がかかる場合もあります
なので、郵便局窓口にて手続きするのが無難ですね。
確実に届けるには「書留」にして送るとか「配達証明」で送るのも一つの方法です。
確実に受け取ってもらえるよう配慮しましょう。
退職届の用紙や封筒はコンビニでも買える?

退職届の用紙や封筒は100均でも買えますが、コンビニではどうでしょう?
家の近くのコンビニで用を済ませたいということもよくあることです。
コンビニもその店舗によって扱っている商品が少々違ってきますので、行って探してみるしかありません。
白い便箋はあったけど郵便番号の枠のない封筒は見つからなかったということもありますし、白地で罫線の入った便箋も見つからないということもあるわけです。
コンビニでも取り扱っているところもあるかもしれませんし、取り扱っていないかもしれません。
お店の人に尋ねてみるのが手っ取り早いかもしれませんね。
ちなみに私の近所にも数店(5〜6店舗)コンビニはあるのですが、全てありました。
100均やコンビニ以外では、通販で買うこともできますし、もしくは文房具店なら多くの種類の文具を置いていることが多いのでおすすめです。
書店の中でも文具類を扱っている書店ならある確率は高いと思います。
他には、「退職願」などの届出書用の用紙セットが販売されているのを見つけました。
退職届専用のものもありました。
こうした市販のものを利用して退職届を作成して提出するのも一つの方法ですね。
めんどくさい退職の手続きは退職代行にまかせてしまいましょう

以上、郵送など退職届の出し方などを紹介してきましたが、「会社を辞める」という状況で、「悩まず退職代行に頼む」という方法もあります。
この手段は、
- もう会いたくない
- 最後までいやみを言われたくない
- 時間は大切
- 辞めると決めたら次
- 自分でやる必要はない
- 辞める会社に時間を使う必要はない
などという人の選択肢の一つになっていて、この考え方は、転職をとてもスムーズかつ効率的に行える手段として利用者が多くなっています。
この裏付けは、
「今の会社を退職する」とした場合、退職代行を利用しますか
というアンケートによると、
その44.7%が「退職代行の利用を検討している」
という数字がデータとして出ています。
(2021年1月)
ほぼ半数です。
この利用希望者の多さからも、
退職代行を使ってスピーディーに辞めることを望む人が増えている
ということです。
時間を大切にする人が多い。とも言えます。
そして、それ以外の半数の人(自分で退職手続きをしている人)は例外なく、
同じ作業に、時間と手間と気を使って退職しています
というわけですが、
一概にはどちらがいいという結論はありません。
しかし、
支障がなければ頼む方が断然楽なのは事実で、それは希望者の多さで裏付けられています。
LINEや電話で相談ができるので、ぜひ気軽にチェックしてみましょう。
↓
即日から出社せず退職


まとめ

退職届の用紙を選ぶときには、白い便箋、白地に罫線の入った便箋、またはコピー用紙から選ぶと良いですね。
封筒は用紙に合わせたサイズのものを選びますが、白で無地のものを選ぶようにします。
これらは、コンビニや100均などでも購入できることもありますが、もし見つからなければ文房具店や大きめの書店などに行くと良いでしょう。
退職届は会社を辞める最後の挨拶ということにもなりますが、「次のスタート」ともいえます。
「どうせやめるから」という気持ちで適当にせず、
- 自分でキッチリと
- 退職代行でスッキリと
いずれにしても、そのスタートの決断はしっかりしたいものですよね。



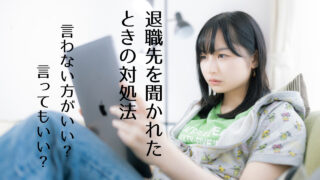


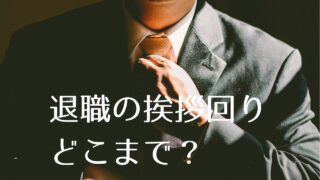


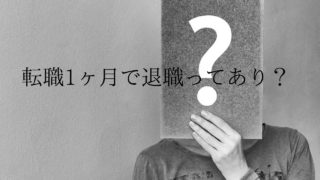

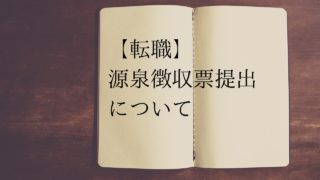
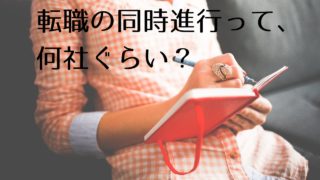
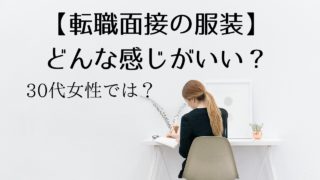





今回はここまで!
COMMENT